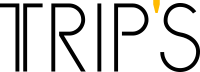世界遺産二条城近くにありながらあまり知られていない「神泉苑」。実は1300年にも及ぶ歴史の中で、日照りが続く日本に雨を降らせたり、疫病の悪霊を祓ったりと幾度となく日本を救ってきたパワーみなぎる場所でもあります。
今回は穴場的な最強パワースポットである「神泉苑」をご紹介いたします。
もとは平安京時代の天皇の遊宴の庭園

昔、この辺り一帯は湿地帯でした。平安京を造営するにあたり、点在する池沼を上手く利用し天皇の遊興の庭園にしたのが、この地域の庭園利用の始まりとされています。その当時、一般庶民は入る事が許されない「禁苑」とされていました。812年には嵯峨天皇が神泉苑で初めて天皇による桜の花見を行ったといわれています。発掘調査で船着き場の木材なども発見されており、優雅な宴が繰り広げられていたことが想像されます。
神の泉という名前の通り豊かに水が湧き出てどんな日照りでも枯れることなく人々の生活のために水を供給していたといわれています。
日本を救う霊場に!

天皇の遊び場から位置づけが変わるきっかけとなったのが空海による雨乞いです。
824年、長く日照りに苦しんでいた人々のために天皇の命を受けた空海が北インドより降雨を司る龍神「善女龍王」を呼び寄せ7日間雨乞いの儀式を行いました。

その結果、なんと3日間雨が降り続き日本を日照りから救うことができました。
人々はこの雨に感謝し善女龍王をこの場所に祀り、その後雨乞いの場所として知られるようになりました。
祇園祭発祥の地、縁結びのパワーも!

神泉苑で一番目立つ善女龍王社に向かってかかる朱塗りの「法成橋」。
この橋はお守りを抱き一つだけ願い事を念じながら渡ると願いが叶うといわれています。
また、この橋の上で1182年、「静御前の雨乞いの舞」が行われ、その舞に魅了された源義経は静御前を側室にしたといわれています。そのことから縁結びのパワースポットとしても知られています。

また、863年には京で疫病が蔓延し、大地震や富士山の噴火など全国で災いが相次ぐ中、その当時の国の数66本の鉾を立て、厄払いを行いました。これが今に続く「祇園祭」です。

入口は御池通沿いと押小路通り沿いの北門の2か所あります。
二条城の建設や火災により全盛期よりもかなり規模は小さくなりましたが今でも人々を惹きつけ、パワーがみなぎる「神泉苑」。ぜひ立ち寄ってみて下さい。
●神泉苑
京都市中京区御池通神泉苑町東入る門前町167