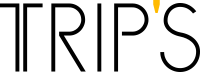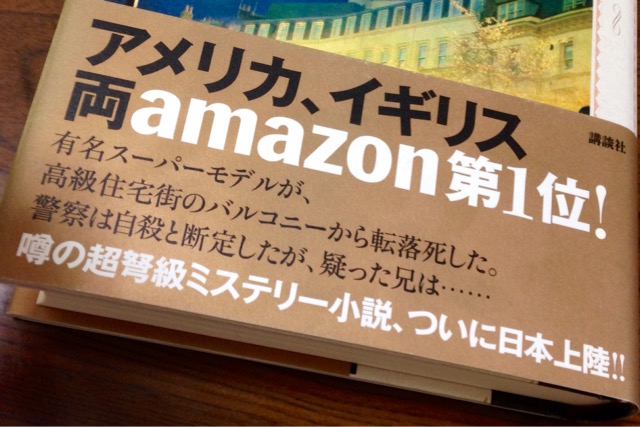川の畔に絵に描いたように苔むす大木。その向こうには欧州でも有数のロマネスク様式のカテドラル「ダラム大聖堂」が見え隠れする。
街の名前、「ダラム(Durham)」の語源はケルト語で「丘の城塞」を意味するdunと古ノルド語で「島」を意味するholmeが語源になっているとされる。街をぐるりと囲うようにウェア川がゆっくりと流れる。
順番からいえばウェア川に囲まれた丘に人が城塞を築いた。川が自然の堀の役割を果たし、丘が城を高みに持ち上げる。特別な土木工事をしなくても防衛が容易な地形をなしている。
ダラム城を眺める
車がせわしく行き交うのをあえて抑止しているのだろうか。川の内側は陸の孤島の様に、隔離された雰囲気が漂う。何とも華奢でか細いプレベンズ橋からみた大聖堂。

ダラム城へと通じるシルバーストリートの橋から、丘の上にあるお城を眺める。この影は一体なんだろう。中世の騎士が今でもこうやってお城勤めをしているのだろうか。現在は、一部、ダラム大学の寮になっているから、学生たちはもしかしたら夜な夜な遭遇しているかもしれない。
この城は、同大学に寄贈されているらしい。大聖堂と共にユネスコの世界遺産に登録されている大事な遺産を、将来のある学生に譲るというのは、粋な心意気だ。でもそこにも何か見えない力が働いているような……。ひょっとして亡霊たちが若者たちへの影響力を強めようとしているのではないか。

奥ゆかしい鐘の音が響く中、アップダウンのある道を体操着を着た学生が列を組んで石畳の上をランニングしている。イングランド北東部の片田舎だが若者が多いのは、由緒正しいダラム大学がある学園都市だからだ。
これだけ美しく歴史と格式のある街で勉学に励んだら、相当に洗練された大人になるのだろう。でも何か特殊な雰囲気が漂い、不思議な力に感化されそうだ。
千年息づく伝統、土葬の墓地は想像を絶する迫力
紀元前のずっと昔から人が住んできた痕跡はあるようで、現在の街の形成は、紀元995年に教会を設立したことに始まる。その後、11世紀にこの地域の領主でもあったダラム司教の守りを固めるためにこの城が建設された。
ざっくり数えて千年前からこの街は続いている。途方もない長い時間に圧倒されながら、こぢんまりとした街を川の内側と外側から、眺めながらグルグルしているうちに日が沈んでゆき、ある地点でふと足が止まった。
何百年前からあるかわからない土葬の墓地。そしてその向こうには大聖堂の光が、異様なまでの空気を作り出している。ま、まずい。幽霊がいつどこから出てきてもおかしくない、何ともスプーキーなテリトリーに足を踏み入れてしまった!

映画のセットでどんなに頑張っても、このヴィジュアルと雰囲気は絶対に出せない。ホラーは大の苦手なのだが、なぜか足がそこから動かない。逃げ出したいような、でもここには何かがある、そんな気がする。恐怖の中の絶対的な美しさに囚われてしまった。
どれだけ時間が経っただろうか。墓場で一夜を越すわけにもいかないので、妙なことが起こる前に、また歩き始めた。
街を少し外れて、歩いていくと幹線道路が現れて、ブンブンと近代的な車が走りかなりの交通量がある。現代のせわしい生活感があり、「あっ、現実に戻ってきたんだ」、そう気がついて我に返った。
ダラムはホラー小説家ブライアン・ラムレイ(Brian Lumley)も輩出しており、『タイタス・クロウの事件簿』や『黒の召喚者』を日本語で読むことが出来る。もう一人のダラム出身の作家、エイダン・チェンバーズ(Aidan Chambers)が、『おれの墓で踊れ』(和訳) というドキっとするような題名の物語も書いている。
やはり、ダラムには、何か言葉では説明のつかないホラーパワーが渦巻いており、住む人々にも影響をあたえているということだろう。